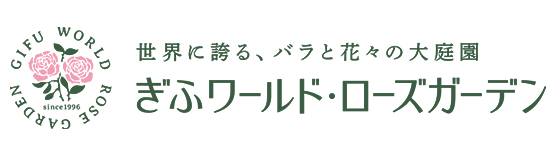冬芝の種まき(オーバーシード)の時期はいつ?
冬になると、高麗芝など日本の夏芝は休眠に入り、地上部が茶色く枯れたようになってしまいます。これは自然な現象ですが、お庭の景観としては少し寂しいものです。
このお悩みを解決するのが「オーバーシード(冬芝の種まき)」です。 今生えている夏芝の上に、寒さに強い「冬芝」の種をまくことで、寒い季節でもゴルフ場のような美しい緑の絨毯を保つことができます。
本ブログでは、冬芝のオーバーシードに最適な時期、成功を左右する下準備の手順、そして種まき後の管理のコツを解説します。
オーバーシードとは?
オーバーシードとは、今ある芝生(夏芝)の上から、別の種類(冬芝)の種を重ねてまく技術のことです。この仕組みを理解するためには、まずは芝生の種類を知る必要があります。
夏芝(高麗芝・姫高麗芝など)
日本の家庭で一般的な芝生です。生育適温が25℃〜35℃と高く、夏の暑さには強いですが、気温が15℃以下になると生育が止まり、茶色く休眠します。
冬芝(ペレニアルライグラスなど)
ヨーロッパなど冷涼な気候が原産の芝生です。生育適温が15℃〜25℃と低めで、日本の冬でも緑色を保ちます。しかし、夏の高温多湿には非常に弱く、多くは夏を越せずに枯れてしまいます。
オーバーシードは、この正反対の生育サイクルを利用します。 秋に夏芝が休眠し始めるタイミングで冬芝の種をまくと、冬の間は冬芝が緑を保ちます。そして春になり気温が上がると冬芝は衰退し、休眠から覚めた夏芝が再び緑になります。このバトンタッチで、一年中緑の芝生(通年グリーン)を実現するのです。
オーバーシードに最適な時期
9月中旬~10月上旬がベスト
オーバーシードの成功は、8割が「時期」で決まります。冬芝の種まきに最適な時期は、9月中旬から10月上旬です。 これは、夏芝の生育が緩やかになり、冬芝の発芽に適した地温(20℃〜25℃)になるのがこの時期だからです。「最高気温が25℃を下回る日が安定して続くようになった頃」が作業開始のベストサインです。
時期を逃すとダメな理由
早すぎる場合(8月下旬〜9月上旬)
まだ地温が高すぎて発芽率が落ちるか、発芽しても暑さで弱ってしまいます。また、まだ元気な夏芝に邪魔をされて根を張れません。
遅すぎる場合(11月以降)
気温が低すぎて発芽率が著しく低下します。発芽しても、本格的な冬が来る前に十分な根を張れず、霜柱で根が持ち上げられて枯れてしまうリスクが高まります。
成功を左右する「種まき前の準備」
種をまく前に、今ある夏芝を徹底的に短くし、土壌の表面を整える「下地づくり」が最も重要です。
芝刈り(低刈り)
まず、夏芝をできるだけ短く刈り込みます(軸刈りにならない程度に10mm〜15mmが目安)。これにより、冬芝の種が土に届きやすくなり、発芽後の日当たりも確保できます。
サッチ除去(スカルプ)
次に、レーキ(熊手)や専用の機械(サッチングマシン)を使い、芝生の根元に溜まった「サッチ(刈りカスや枯れ葉の層)」を強力にかき出します。
サッチの層が厚いと、まいた種が土に触れられません。サッチの上で発芽しても、根が土に張れず、すぐに水切れで枯れてしまいます。種が土に直接触れられるよう、徹底的に取り除くことが成功につながります。
冬芝の種まきの手順
- 種まき
準備した地面に、冬芝の種を均一にまきます。一般的なペレニアルライグラスの場合、1平方メートルあたり約40〜50gが目安です。 均一にまくコツは、まく量を半分に分け、「タテ方向」と「ヨコ方向」の2回に分けてまく(クロスまき)方法です。これにより、まきムラを最小限に抑えられます。 - 目土(被土)
種をまき終わったら、種が隠れる程度(2〜3mm程度)に「目土(めつち)」を薄くかけます。これを「被土(ひふど)」といい、種を乾燥や鳥の被害から守る重要な役割があります。 - 鎮圧
板や足などで軽く踏み固め(鎮圧)、種と目土を密着させます。この作業で、種が土の水分を吸いやすくなり、発芽が揃います。 - 【重要】水やり
種まき後、最も重要なのが水やりです。発芽するまでの約1〜2週間は、絶対に土の表面を乾かしてはいけません。朝夕の2回、シャワー状の優しい水でたっぷりと水やりを続けます。
オーバーシード後の管理方法
水やり
無事に発芽し、芽が揃ってきたら、徐々に水やりの回数を減らします。冬場はそれほど水分を必要としないため、土の表面が乾いていたら、午前中の暖かい時間帯に1回水やりをする程度で十分です。夕方以降の水やりは、夜間に地面が凍結する原因になるため避けましょう。
芝刈り
種まきから約3〜4週間で草丈が5〜6cm程度に伸びたら、最初の芝刈りのタイミングです。芝刈りをすることで、芝が横にも広がるよう促され、密度が高い芝生になります。 冬場の冬芝の刈高は、夏芝(高麗芝)よりも長めの30mm〜40mm(3〜4cm)程度を保ちます。冬は日照時間が短いため、短く刈りすぎると光合成ができず、生育不良になるため注意しましょう。
施肥(肥料やり)
冬芝は冬でも生育を続けるため、肥料が必要です。発芽して芝刈りを始めた頃に1回、その後は月に1回程度、緩効性の化成肥料(芝生用)を与えます。特に窒素(N)は葉の色を濃くするため、適度な施肥で美しい緑色を保てます。
春の管理(夏芝へ切り替え)
冬の間、目を楽しませてくれた冬芝ですが、春には役目を終えます。気温が上がり地温が25℃を超えてくる4月〜5月頃、冬芝は暑さで生育が衰え、徐々に枯れ始めます。
このタイミングで、休眠から覚めた夏芝が下から伸びてこようとします。夏芝の成長を助けるために、芝刈りの高さを徐々に低くしていきます。邪魔な冬芝を短く刈り込むことで、夏芝に日光が当たりやすくなり、スムーズなバトンタッチができます。
よくある失敗と対処法
種をまいても発芽しない
主な原因は、時期が早すぎたり遅すぎたりして地温が合わないこと、水やり不足による乾燥、またはサッチ除去が不十分で種が土に届いていないことです。最適な時期(地温20〜25℃)を守り、発芽までは絶対に土を乾かさないこと、種まき前のサッチ除去を徹底することが対策です。
芝が密集しすぎてカビが発生する
種のまきすぎや、水はけ・風通しが悪いことが原因です。種は適量を守り、密集して蒸れる場所は刈り込みをしっかり行って風通しを良くしましょう。
色ムラができる
種のまきムラや肥料ムラが原因です。種はクロスまきで均一にし、肥料も散布機などを使うと均一にまきやすくなります。
まとめ
冬の茶色い芝生を鮮やかな緑に変える「冬芝のオーバーシード」。この作業の成功の鍵は、9月中旬から10月上旬という「時期」を逃さないことです。そして、種まき前には徹底的な「サッチ除去」で下地を作り、発芽までは「絶対に乾かさない」水やり管理を徹底することが重要です。
最初は手間がかかると感じるかもしれませんが、基本のステップさえ守れば、冬でもゴルフ場のような美しい緑の芝生を実現できます。ぜひチャレンジしてみてください。