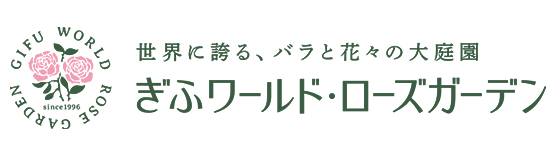コキアの育て方|種まきの時期と秋に真っ赤に紅葉させるコツ
春から夏の柔らかな緑色と丸い形、秋には燃えるように真っ赤に染まる姿で庭を彩る「コキア(ホウキグサ)」。一年草(まいた年に枯れる植物)ですが、その育てやすさと美しさで人気があります。一見、管理が難しそうに見えますが、いくつかのコツさえ押さえれば、初心者でも種から簡単に育てられます。
本ブログでは、コキアの栽培で失敗しないための「種まきの時期」「間引きの重要性」、そして「秋に美しく紅葉させる条件」まで、育てるポイントを順を追って解説します。
コキアの育て方|種まき編
コキア栽培は種まきから始まります。最初でつまずかないよう、ポイントを押さえましょう。
種まきの時期(3月下旬~5月)
種まきは、気温が安定して暖かくなる3月下旬から5月上旬が目安です。コキアは寒さに弱いため、遅霜の心配が完全になくなってから屋外にまきましょう。
発芽に適した温度は20℃〜25℃です。気温が低いと発芽しません。気温が安定しない時期は、室内でポットにまいて育てる(ポットまき)のも確実な方法です。
発芽には「光」が必要
コキアは、発芽するために光を必要とする「好光性種子(こうこうせいしゅし)」です。種の上に土を厚くかぶせすぎると、光が届かず発芽率が著しく下がります。種をまいたら、土をかけるかかけないか程度のごく薄く(1〜2mm)かぶせるか、土の表面を軽く押さえて種を密着させるだけにします。発芽するまでは、土の表面を乾燥させないよう、霧吹きや優しい水で管理しましょう。
コキアの育て方|植え付けと間引き編
間引きで形が決まる
コキアをふんわりとした丸い形に育てるには、「植え付けの間隔(株間)」が最も重要です。種が密集して発芽したら、本葉が2〜3枚出たタイミングで、生育が悪いものを引き抜き(間引き)、元気な株を残します。最終的に、株と株の間隔は30cm〜40cmは確保するのが理想です。
「もったいない」と感じるかもしれませんが、ここが最大のポイントです。間隔が狭すぎると、お互いが邪魔をしてひょろひょろと縦にばかり伸びてしまいます。その結果、蒸れて病気になったり、風ですぐに倒れたりする原因になります。ふんわり丸く育てるには、十分なスペースが不可欠です。
コキアの育て方|夏の管理編
日当たり
一日中、よく日が当たる場所で育ててください。コキアは日光が大好きです。日当たりが悪いと、光を求めて枝がひょろ長く伸び、倒れやすくなるだけでなく、秋の紅葉も色あせてしまいます。
水やり
コキアは乾燥した土地の植物なので、湿気が多すぎる状態を嫌います。
-
地植えの場合:
根付いてしまえば、よほど雨が降らない日が続く場合を除き、基本的に水やりは不要です。 -
鉢植えの場合:
土の表面が乾いたら、鉢底から水が出るまでたっぷりと与えます。常に土が湿っている状態は根腐れの原因になるため、土が乾いてから水を与える「メリハリ」が重要です。
肥料は「控えめ」に
ここがコキアを倒れにくくし、紅葉を成功させる重要なポイントです。肥料(特に窒素成分)が多すぎると、枝葉が異常に茂り、茎が弱々しく育ってしまいます。その結果、少しの風雨ですぐに倒れてしまいます。また、秋になっても葉の緑色が抜けず、紅葉しにくくなる原因にもなります。肥料は、植え付けの時に土に少量を混ぜ込む程度で十分です。
コキアの育て方|真っ赤に紅葉させるコツ
コキア栽培の一番の見どころは、秋の紅葉です。9月下旬から10月中旬にかけて、気温が下がってくると徐々に色づき始めます。これは、カエデやモミジと同じ仕組みで、昼と夜の寒暖差によって、葉の緑色の色素が分解され、赤い色素が作られることで起こります。
美しい真紅に染めるためには、以下の3つがポイントです。
-
十分な日光:
赤い色素は、日光がないと作られません。秋になっても日当たりが良い場所で管理することが大切です。 -
肥料を控える:
秋になっても土に肥料分(特に窒素)が多く残っていると、緑色の色素がなかなか分解されず、紅葉が始まらないか、くすんだ色になります。 -
寒暖差:
秋の冷え込みが、紅葉の引き金になります。
まとめ
コキアの栽培は、ポイントさえ押さえれば決して難しくありません。「日当たりが良い場所」で、「株の間隔を30cm以上しっかり空け」、「肥料と水を与えすぎない」こと。これが、コキアを丸く元気に育て、秋に美しく紅葉させる最大の秘訣です。手をかけすぎず、その魅力的な色の変化を楽しんでください。