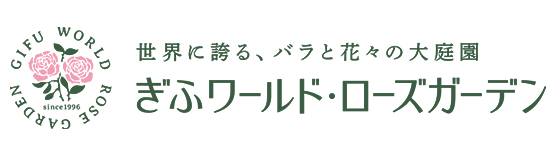常緑樹・針葉樹の剪定時期はいつ?
庭の印象を一年中支えてくれるシマトネリコやコニファーなどの常緑樹・針葉樹。しかし、「いつ剪定したらいいか分からない」「切りすぎて枯れてしまった」といった失敗の声も多いのが事実です。
本ブログでは、造園のプロの視点から、常緑樹・針葉樹の正しい剪定時期と、初心者でも失敗しない基本の切り方、注意点を解説します。
なぜ剪定が必要なのか?
剪定は、見た目を美しくするためだけに行うものではありません。木を健康に保つために不可欠な作業です。主な目的は、混み合った枝を減らして「風通し」と「日当たり」を改善することです。これにより、内部の蒸れを防ぎ、病気や害虫の発生を抑えることができます。
また、不要な枝を切ることで、木がエネルギーを新しい芽や花芽に集中できるよう促します。木が大きくなりすぎるのを防ぎ、適切なサイズに保つことで、木の健康寿命を延ばすことにも繋がります。
常緑樹と針葉樹の剪定で「避けるべき時期」
常緑樹・針葉樹の剪定で最も重要なのは「時期」です。まず、木に大きなダメージを与えるため、原則として剪定を避けるべきなのは以下の時期です。
真夏(7月〜8月)
人間が夏バテするように、木も夏の高温と乾燥で弱っています。この時期に剪定(=傷口を作ること)をすると、切り口から水分が蒸発しすぎたり、強い日差しで切り口付近が「日焼け」を起こしたりして、枝が枯れ込むリスクが非常に高くなります。
真冬(12月〜2月)
気温が低すぎると、木の活動はほぼ停止します。この時期に太い枝を切ると、木に体力がないため切り口の傷が春までふさがりません。結果として、切り口から寒風が入り込んで枯れたり、病原菌に侵されたりする原因になります。
常緑樹・針葉樹の最適な剪定時期
常緑樹・針葉樹の剪定は、木の活動が活発すぎず、かといって休眠しすぎてもいない「春」と「秋」が基本となります。
3月~6月(春〜初夏):軽剪定
新芽がぐんぐん伸び始めるこの時期は、冬の間に混み合った枝や、新芽が伸びすぎて乱れた部分を整理する「軽剪定」に最適なタイミングです。特に梅雨入り前(5月下旬〜6月上旬)までに風通しを良くしておくことで、夏の高温多湿による蒸れを防ぎ、病害虫の発生を抑えることができます。
ただし、あくまで「軽剪定」です。これから光合成を活発に行う新芽をすべて切り落とすような強い剪定は避けましょう。
9月~11月(秋〜初冬):基本剪定
夏の暑さが和らぎ、木の成長が落ち着いてくるこの時期は、樹形を整える「基本剪定(整枝剪定)」に最適です。夏に伸びすぎた枝を切り詰め、本格的な冬が来る前に樹形を美しく仕上げます。この時期にはすでに来年の春に向けた芽が準備されていることも多いため、芽を確認しながら形を整えます。霜が降りるほど寒くなる直前までには終わらせるのが理想です。
常緑樹と針葉樹|剪定方法の違いと注意点
常緑樹(シマトネリコ、キンモクセイ、オリーブなど)
常緑樹とは、葉が広く平たい「広葉樹」のうち、一年中葉をつけている木を指します。
- 自然な樹形を活かす
常緑樹の剪定は、人工的な形に刈り込むのではなく、その木が本来持つ自然な樹形を活かすのが基本です。枝が分かれている付け根(分岐点)で切るようにし、枝の途中で切る「ぶつ切り」は樹形が暴れる原因になるため避けましょう。 - 「やりすぎない」が鉄則
冬でも光合成を続けているため、一度に大量の葉を切り落とす「強剪定」を行うと、木全体が極端に弱ってしまいます。一度の剪定で切る量は、木全体の枝葉の2〜3割程度までに必ず留めてください。「少し物足りないかな?」と思うくらいで止めるのが成功のコツです。
針葉樹(コニファー類、マツ、ヒノキなど)
針葉樹は、葉が針のように細長い木の総称で、常緑樹よりもさらにデリケートな剪定が求められます。
- 【最重要】葉のない古い枝で切らない
コニファー類の多く(ゴールドクレストなど)は、葉がついていない茶色い幹(古い枝)の部分まで深く切り戻すと、そこから二度と新芽が出ません。その部分だけ穴が空いたようになり、修復不可能になるため、絶対に避けてください。 - 先端を軽く摘む剪定が基本
剪定は、必ず「緑色の葉が残る範囲」で行います。新芽の先端を軽くハサミで摘む(ピンチする)ようにして形を整え、密度を高めます。成長が早いものが多いため、一度に強く切るのではなく、適期である春と秋の年2回、こまめに軽く整えるのが美しい形を保つ秘訣です。
剪定で切るべき「不要な枝」
どこから切ればいいか迷ったら、まず以下の「不要な枝(忌み枝)」から優先的に取り除いてみましょう。これらの不要枝を整理するだけでも、風通しは劇的に改善されます。
- 枯れ枝・病害枝:最初に取り除きます。
- 内向枝:幹に向かって内側に伸びる枝。風通しと日当たりを悪くする元凶です。
- 交差枝:他の枝と交差している枝。枝同士が擦れて傷の原因になります。
- 徒長枝:幹から勢いよく真上に伸びる枝。樹形を乱し、他の枝の養分を奪います。
剪定後のアフターケア
剪定は「切って終わり」ではありません。木がダメージから回復するためのケアも重要です。太い枝(目安として親指以上)を切った後の切り口は、人間でいう「大きな傷口」です。そのまま放置すると雨水や病原菌が侵入する原因になります。切り口に殺菌・保護効果のある「癒合剤」を塗ることで、木の回復を助け、病害を防ぎます。
また、剪定で落ちた枝葉、特に病気や害虫がいた枝葉を庭に放置すると、そこから菌や害虫が広がる原因になります。必ず集めて適切に処分しましょう。
まとめ
常緑樹・針葉樹の剪定は、落葉樹とは違うデリケートさがあることを理解するのが重要です。剪定時期は「3月~6月(軽剪定)」と「9月~11月(基本剪定)」の年2回を基本とし、木が弱る「真夏」と「真冬」は必ず避けます。
常緑樹は「一度に切る量は2~3割まで」を守り、針葉樹は「葉のない古い枝で切らない」ことを徹底してください。無理に形を作ろうとせず、木が本来持つ自然な枝の流れを読み取り、不要な枝を整理して風通しを良くしてあげる。それが、庭木と長く美しく付き合っていく秘訣です。